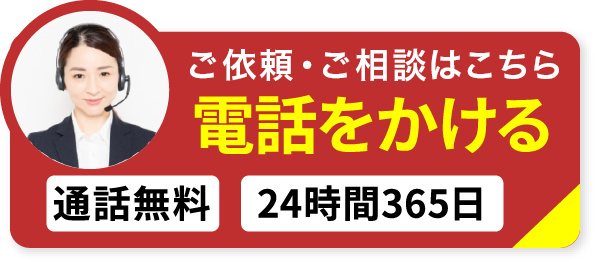電話で
お問い合わせ
-
福島
0120-554-262 -
茨城
0120-554-278 -
岩手
0120-554-579 -
山形
0120-554-624 -
千葉
0120-554-262
葬儀の知識
親族が知っておきたい【法事のマナー】を種類ごとに解説
2025/2/25作成
2025/2/25更新

ご親族がお亡くなりになり、葬儀やその後の一連の法事を執り行なうことになったものの、「初めてのことでマナーが分からない」「参列者や招待客に失礼があるのでは」と、マナー面で不安に思っている方はいらっしゃらないでしょうか? 今回は親族が知っておくべき基本的なマナーについて、葬儀・法要の場面ごとに分けて解説します。 法事のマナーについて迷われる場合は、以下より無料でご相談やお問い合わせを承ります。
目 次
葬儀(通夜式・告別式)のマナー
まずは通夜式や告別式で親族が知っておくとよいマナーをご紹介します。
葬儀の進行などは葬儀社に任せられるものの、一般参列者への対応など親族にしかできない事柄も多くあり、場面ごとに細やかな気遣いが求められます。
早めの到着とスケジュールの確認
同居の親族は葬儀場に泊まり込むことも多いですが、そうでない場合も、余裕を持って通夜式や告別式1~2時間前には会場に着くようにします。
一般参列者からの問い合わせなどに対応できるよう、葬儀の流れや終了時間、トイレの場所やタクシーの利用などを確認しておきましょう。
一般参列者への対応
お悔やみを受けた場合には、「本日はお忙しいところお越しいただきありがとうございます」など、親族として丁寧にお礼を述べましょう。
受付
参列者と最初に挨拶を交わす場のため、失礼のないよう丁寧に対応します。
香典を受け取る時は、「ありがとうございます」「頂戴いたします」ではなく、「お預かりいたします」が適当です。
受付では、香典をいただき記帳を促す人、返礼品を渡して会場へ案内する人などに分けて決めておくと進行がスムーズになります。
会計
間違いや不備のないよう、複数人で対応すると安心です。
「誰からいくら香典をいただいたか」「お花やお供物を贈っていただいた方」などを集計しておくと、香典返しやお礼状の発送の際に役立ちます。
湯茶接待
早く到着して控室で待っている親戚や故人の親しい友人などにお茶を出してお迎えします。
言葉を交わすときは「重ね重ね」「たびたび」「つくづく」などの重ね言葉を使わないよう注意しましょう。
雑務
お茶やお菓子、ストッキングなど、必要なものや足りないものなどの買い出しも親族がすすんで行きましょう。
その他、通夜振る舞いや精進落としにはできる限り参加し、参列のお礼を伝えるのが望ましいですが、大声で話したりお酒を飲んでハメを外すことがないよう気をつけましょう。
忌日法要(初七日・四十九日・百か日)のマナー

忌日法要とは、故人が亡くなってから七日ごとに行う法要のことで、初七日から四十九日法要まで7回の忌日法要があります。
葬儀と併せて行うことの多い初七日から7日ごとに、亡くなってから14日後の二十七日(ふたなのか)、21日後の三十七日(みなのか)と続き、49日後の七十七日(しちしちにち・なななぬか)が四十九日法要となります。二十七日から六十七日の法要は省略されることが多く、行う場合でも遺族のみで自宅で済ませるケースが多いようです。
故人が亡くなってから100日目に行う百か日は、忌明け後初めての法要となり「卒哭式(そっこくしき)」とも呼ばれるこの百か日法要を大事にしている地域もあります。
法要では、僧侶の読経や焼香など供養を行ったあと、多くの場合は近親者と友人などで会食が行われます。
忌日法要は喪服が基本ですが、親族で話し合って「平服で」となれば黒や紺などのダークスーツやワンピースなどでも構いません。
案内状は法要開催日の1〜2ヶ月前までに届くように送りましょう。送る範囲は、近しい親戚や故人と縁の深かった知人友人などです。血縁では遠い関係でも、付き合いの深かった親戚には案内状を送ります。
ただし、高齢の方や妊婦さん、住まいが遠方などの事情で移動が難しい場合は負担になってしまうこともあるため、先方の意向を伺ってから案内状を送りましょう。
法事の案内状を作成や送付する際のマナーと案内文の例は以下の通りです。
- 時候の挨拶を入れる
- 句読点を使わない
- 縦書きにする
- 文頭の一字下げをしない
- 忌み言葉を使わない
- 弔事用の切手を貼る
- 封筒に入れて出す場合は、「不幸が重なる」という意味から二重封筒を使わない
【法要の案内状の文例】
| 謹啓 春暖の候 皆様方におかれましてはご清祥のことと存じます亡父〇〇〇〇の葬儀に際しましては皆様より温かいご厚志を賜り感謝申し上げます
このたび 次のとおり四十九日法要を営みたいと存じます 皆様のご参会をお願いしたくご案内申し上げます 謹白 記 日時 令和◯年◯月◯日(◯曜日)午前10時より 会場 〇〇会館 住所 東京都〇〇区〇〇 電話 〇〇(〇〇〇〇)〇〇〇〇 尚 法要後にささやかではございますが会食の席をご用意しております 以上 令和◯年◯月◯日 東京都〇〇区〇〇 施主〇〇〇〇 お手数とは存じますが◯月◯日までにご都合を返信用はがきにてお知らせください |
参加の可否を尋ねるため、封筒で送る場合は返信用はがきを同封し、はがきで出す場合は往復はがきを使用しましょう。
そのほか忌日法要のマナーについて迷ったらお気軽にさがみ典礼までご相談ください。
▼24時間365日、無料で相談受付中
年忌法要(一周忌・三回忌・七回忌など)のマナー

年忌法要とは故人の命日に行う法要のことで、一周忌、三回忌、七回忌と、3や7がつく法事が続きます。3と7は仏教において特別で意味のある数字として扱われているためです。
近年では核家族化やライフスタイルの変化から法事を省略する傾向があり、一般的には三十三回忌まで行うといわれているものの、七回忌や十三回忌で弔い上げとするケースもあります。何回忌まで行うかはお住まいの地域や宗派によって異なるため、親族やお世話になっている寺院などに確認すると良いでしょう。
また、年忌法要を命日より遅れて行うのはタブーとされているため、命日当日、もしくは少し前に設定します。
年忌の数え方は1年目の一周忌以降、2年目で三回忌、6年目で七回忌と、故人の亡くなった年を含めて数えるため注意が必要です。
三回忌までは親族と友人などで法要を行い、七回忌以降は親族のみ、それ以降は親子やきょうだいなど近しい親族のみで行うなど、規模が小さくなっていく傾向があります。
服装は、三回忌までは準喪服が基本ですが、七回忌以降は略喪服や平服で良いとされています。ただし、皮革製品や毛皮など、殺生を連想させるものは避けましょう。
案内状送付の時期や書き方の注意点は、忌日法要の場合と同様です。
法事のマナーで困ったら、さがみ典礼へご相談下さい

法事のマナーは色々あって難しい…と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、マナーの本質は、故人の冥福を祈る思いとお世話になった方々への感謝と敬意を示すことであり、形を気にしすぎるよりも、相手を不快にさせない思いやりの心を持って振る舞うことがもっとも大切です。
もし、法事のマナーに自信がなく心配な方は、プロに相談すると安心です。
関東・東北エリアに230カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間47,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習にそって、皆様に気持ちよくお過ごしいただけるようなマナーを提供し、ベストなお葬式のかたちが実現するようお手伝いさせていただきます。
今すぐ法事のマナーについて相談したい方、今すぐではないが情報を知っておきたい方は、お気軽に以下よりお問い合わせ下さい。親身になって相談を承ります。
▼24時間365日、無料で相談受付中


葬儀のことでお困りの時はさがみ典礼にお電話ください
葬儀のことでお困りの時は
さがみ典礼にお電話ください。
-
福島
-
岩手
-
茨城
-
山形
-
千葉
電話でお問い合わせ
-
福島
0120-554-262 -
茨城
0120-554-278 -
岩手
0120-554-579 -
山形
0120-554-624 -
千葉
0120-554-262